ビジネスで成功するためには会計の知識が不可欠です。
よって、ビジネスで成功するための勉強として会計を学ぶべきです。
事業を理解する上では数字を理解しなければいけません。
会計はビジネス上の言語です。早いうちに習得して自分のものにするに越したことはありません。
ーウォーレン・バフェット
Accounting is the language of business and there’s nothing like getting it early and getting it into your system.
Warren Buffett surprises teen cancer patient on CNBC
では現時点で会計知識がない人は何を勉強すべきか?
会計知識がほぼない方には、簿記3級取得がおすすめです。
学習時間はそれほどかかりませんし、講座や教材は豊富で費用は安く済みます。
本記事最後に無料で受講できるおすすめの簿記3級講座を紹介します。
簿記3級では会計の基本的なことが相当多く身につきますので、コスパのよい資格です。
1 会計はビジネス言語 | 成功するには習得必須とバフェットも言っている
将来金持ちになるため、ビジネスで成功するためにはどうしたらいいか?
これについてウォーレン・バフェットが以下のように学生から質問を受けました。
10代の私たちが、将来に備え、あなたのように成功するために、何をするのがおすすめですか?
(“What recommendations would you give us as teenagers to prepare for our future and become as successful as you?”)
(Afternoon Session – 1998 Berkshire Hathaway Annual Meeting (cnbc.com))
バフェットが回答の中で真っ先に答えたのは、「会計を学ぶべき」でした。
もしあなたがビジネスに興味があるなら、20代前半までに会計を学ぶべきだと思います。会計はビジネスの言語です。
(if you’re interested in business, I definitely think you ought to learn all the accounting you can by the time you’re in your early 20s. Accounting is the language of business.)
Afternoon Session – 1998 Berkshire Hathaway Annual Meeting (cnbc.com)
おそらくこの記事を読んでいる人の多くは、10代ではなく、20代以上だと思います。
20代以上の読者が、ビジネスで成功したいなら、会計の勉強はどうしたらいいか?
すぐ始めるしかありません。
早い方がいい。
バフェットは会計の重要性について以下のように続けます。
(会計がビジネスの言語といっても)完璧な言語というわけではありませんから、その言語の限界も、あらゆる側面から知っておかなければなりません。
that doesn’t mean it’s a perfect language, so you have to know the limitations of that language, as well as all aspects of it. So I would advise you to learn accounting.
同上
会計税務のわからないことが出てきたら会計士や経理がうまくやってくれるだろうと思ったら大間違いです。
会計という言語がビジネスをどのように描写するのか知っておくべきです。
2 会計の勉強は簿記から始めよ
会計の勉強をどう始めるかについて、バフェットの右腕であるチャーリー・マンガーは、まず簿記を学ぶことを勧めています。
簿記の基本的なルール、足し算と引き算のようなものを学ぶ。
you start by learning the basic rules of bookkeeping, which are sort of like the basic rules of addition and subtraction.
Morning Session – 2003 Berkshire Hathaway Annual Meeting (cnbc.com)
会計初心者が勉強するなら簿記3級の勉強から始めましょう。
とてもコスパのいい資格です。
学習費用は安く(後述するとおりやれば無料受講できる講座あり)、勉強時間は短く済み、会計の重要な部分が学べます。
3 簿記の講座(無料受講できる講座あり)
私は、かつてLECの日商簿記の講座を買って勉強しました。3級はとてもわかりやすかったです。2級になったら同じ講師だったにもかかわらず、だいぶ手抜きというかわかりにくくなりました。
私はお金を支払って簿記講座を買いました。
「ものは試しとはいえお金がかかるのはちょっと。。」という人もいるでしょう。
そんな人に朗報です。
公認会計士資格スクールであるCPA会計学院は、無料資料請求をすると、なんと無料で簿記3級レベルの講座が受けられます。
CPA会計学院資料とともに送付されてくる教材は以下の通りです。
公認会計士講座簿記入門Ⅰ(簿記3級相当)の視聴動画URL
テキスト(PDF)
問題集(PDF)
昔はDVDと紙のテキストが送られてきましたので、今は全て電子媒体に代わったようです。
CPA会計学院の講座は、公認会計士試験合格を目指す硬派な講座です。黒板を使って進められます。
「え?公認会計士?受験するつもりないんだけど。。難しそう・・」と思われる方もいるかもしれませんが、公認会計士試験を考えてなくても大丈夫ですし、難しいということもありません。とてもわかりやすい。
ネット上で半端に無料で教えられているいいかげんな講座とはわけが違います。
また、CPA会計学院のことを知らない人も多いかもしれませんが、もちろん怪しい学校ではありません。
CPA会計学院は、1968年に開された日本で一番最初の公認会計士資格スクールです。
そして、CPA会計学院のウリはなんといっても公認会計士試験の合格者占有率の高さです。2022年の合格者占有率は41.6%とされています。
CPA会計学院のデメリットは、事務局が弱いところかもしれません。CPA会計学院から送付された教材は複数回ミスがありました。。(司法試験予備校ではこんなことなかった!)
事務局は貧弱かもしれませんが、講座自体はしっかりしています。
まずは無料資料請求をしておまけでついてくる簿記3級講座を腕試しに受講してみましょう。
CPA会計学院のポイント
- 伝統ある公認会計士資格スクール
- 無料の簿記3級講座が資料請求で付いてくる
▼CPA会計学院の公式サイト









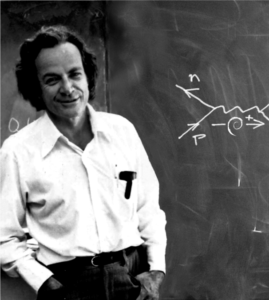

コメント
コメント一覧 (5件)
[…] 転職キャリアルール 会計の初心者には簿記3級がおすすめ | 転職キャリアルール 事業を理解する上では数字を理解しなければいけません。 会計はビジネス上の言語です。早いうちに […]
[…] ビジネス法務パーソン(弁護士)が会計を勉強するには簿記3級がおすすめ […]
[…] なお、会計がさっぱりだという人が会計を勉強するには簿記3級がおすすめです。 […]
[…] あわせて読みたい ビジネスで成功するには会計を勉強せよ | 簿記3級はどうか ビジネスで成功するためには会計の知識が不可欠です。 よって、ビジネスで成功するための勉強として […]
[…] あわせて読みたい ビジネスで成功するには会計を勉強せよ | 簿記3級はどうか ビジネスで成功するためには会計の知識が不可欠です。 よって、ビジネスで成功するための勉強として […]